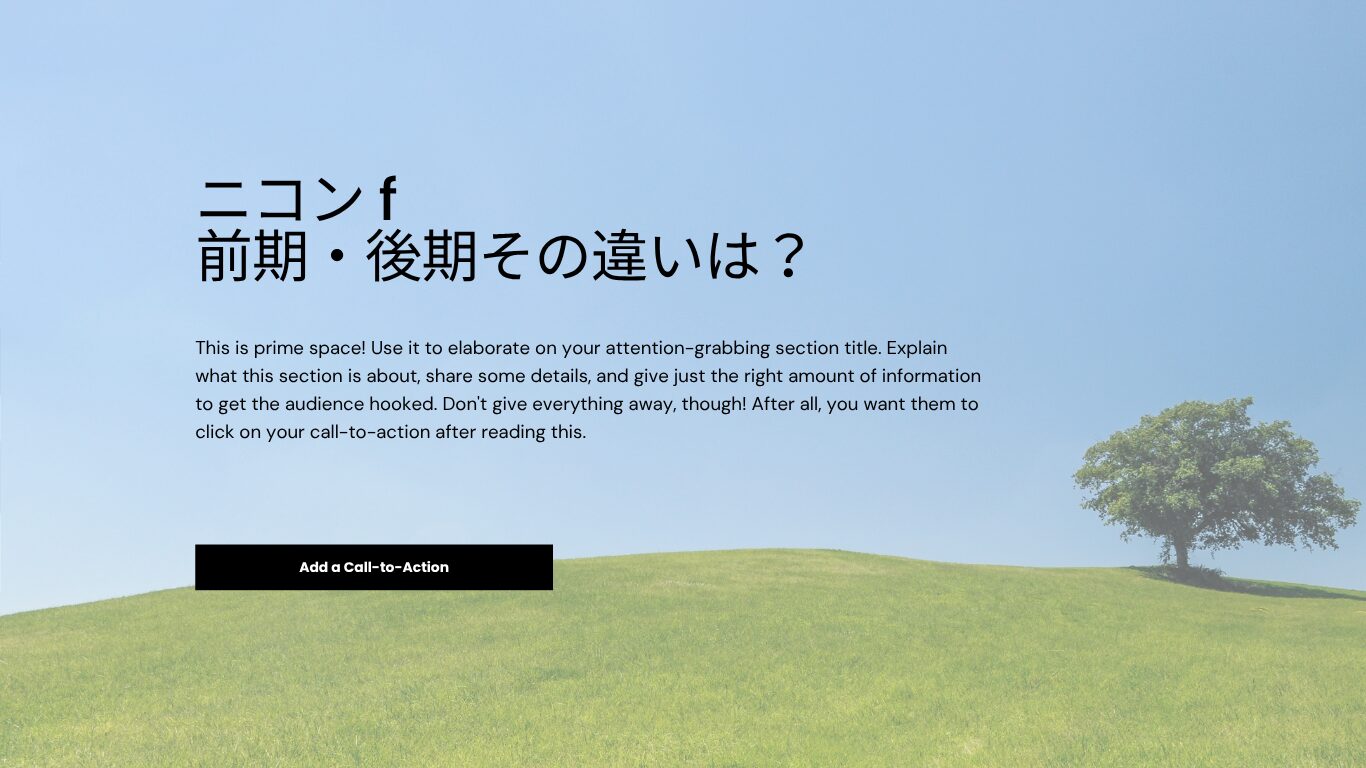フィルムカメラの黄金時代を築き上げ、今なお多くの写真愛好家を魅了し続ける歴史的名機、ニコンF。
その無骨ながらも美しいデザインと、プロの過酷な要求に応え続けた圧倒的な信頼性から、いつかは手にしたい一台として憧れを抱いている方も多いのではないでしょうか^^
しかし、中古市場でニコンFを探し始めると、前期・中期・後期といった複数のモデルが存在することに気づき、「一体何が違うのだろう?」という疑問に突き当たります。
そこで、この記事では、ニコンfの前期と後期の違いという核心的なテーマを現役記者の私が解説します。
まずは、ニコンFの歴史を紐解き、なぜニコンFが伝説となった理由があるのか、その背景を探ります。そして、Nikon F アイレベルとは何?また多くの人が気になるニコンF アイ レベルの欠点は何?といった基本的な疑問にも丁寧にお答えします。
さらに、ニコン Fの初期型の見分け方の鍵となる象徴的なニコンFの富士山マークについてや、コレクター垂涎の的である希少なニコンF 640の特徴とは何かについても深く掘り下げて解説。実用的な知識として、ニコンFの製造番号から製造年を特定する方法や、ニコンFの当時の価格はいくらでしたかという興味深いトリビア、さらにはメンテナンスにも役立つニコンFのファインダーの外し方まで、具体的かつ網羅的にご紹介します。また、進化の系譜を理解するために、後継機であるニコン F2の前期と後期の違いや、多くのユーザーが気にするニコンFマウントは生産終了ですかという将来的な疑問にも触れ、あなたのカメラ選びを総合的にサポートすることをお約束します^^
ニコンfの前期と後期、その違いを深掘り

- ニコンFの歴史を紐解く
- ニコンFが伝説となった理由
- ニコンFの当時の価格はいくらでしたか?
- ニコンFの初期型の見分け方
- ニコンFの富士山マークについて
- 希少なニコンF 640の特徴とは
ニコンFの歴史を紐解く
ニコンFは、1959年6月に日本光学工業(現:株式会社ニコン)から華々しくデビューした、同社初の35mmフィルム一眼レフカメラです。
この一台のカメラが、その後の世界のカメラ史を塗り替えるほどの大きなインパクトを与えました。当時、プロフェッショナル向け高級カメラ市場は、ドイツのライカやコンタックスに代表されるレンジファインダーカメラが席巻していました。ニコンもまた、傑作機「ニコンSP」でその地位を確立していましたが、社内ではすでにレンジファインダーカメラの構造的な限界(特に望遠レンズや接写時のパララックスの問題)も認識され始めていました。
このような状況下で、ニコンFの開発は高性能レンジファインダー機「ニコンSP」と並行して進められました。この同時開発という方針は、ニコンFの成り立ちに大きな影響を与えています。例えば、多くのユーザーから指摘される独特なシャッターボタンの位置や、裏蓋が完全に取り外せる構造などは、ニコンSPとの部品共通化や操作性の統一を図った名残なのです。
しかし、ニコンFは単なるSPの派生モデルではありませんでした。ニコンの公式サイトの記述によると、開発当初からプロの使用を前提としたシステムカメラとして設計され、「視野率ほぼ100%のファインダー」「世界初の実用的なモータードライブ対応」「完全自動絞り機構」といった、当時としては革命的とも言える先進技術が惜しみなく投入されました。これらの機能は、その後のプロ向け一眼レフカメラのデファクトスタンダードとなり、ニコンFは登場と同時に「一眼レフカメラの一つの完成形」として市場に受け入れられたのです。結果として、1974年に生産を終了するまでの約15年間、一度も基本的な設計を変えることなく製造され続けた、驚異的なロングセラーモデルとなりました。
ライター
ニコンSPという最高峰のレンジファインダー機を自ら作りながら、その未来を見据えて一眼レフという新たな道を切り拓いたんですね。ニコンの先見性には驚かされます。
前期型・中期型・後期型にわたる仕様の変遷を押さえることは、価値ある個体を見極める上でも重要です。「Nikon F2」の仕様やフォトミックファインダーのタイプ別違いについては、こちらの記事で解説しています。
ニコンFが伝説となった理由

ニコンFが単なる「古いカメラ」ではなく、「名機」「伝説」として今なお熱く語り継がれる理由は、その先進的な機能性に加え、他の追随を許さない圧倒的なまでの堅牢性と信頼性に集約されます。
ボディの心臓部には堅牢なアルミ合金ダイキャストを採用し、外装のカバー類には真鍮を用いるなど、贅沢な素材で構成されていました。そして、その信頼性を象徴するのが、世界で初めて実用化されたチタン箔のフォーカルプレーンシャッターです。従来の布製シャッターは、太陽光で焼けて穴が開いてしまう弱点がありましたが、チタン幕の採用によりその問題を根本から解決し、耐久性を飛躍的に向上させました。
その真価は、極限状況であるプロの現場でこそ発揮されました。朝鮮戦争で「凍らないニコン」として名を馳せたレンズの潤滑油技術はFにも受け継がれ、極寒地での信頼性を確保。そして最も有名なのが、ベトナム戦争で多くの報道カメラマンに愛用された数々のエピソードです。
「取材中に銃弾を受けたが、貫通せずに中のフィルムを守り、カメラも修理後再び使えるようになった」という、にわかには信じがたい逸話が残っているほど、ニコンFはカメラマンにとって命を守る盾であり、どんな状況でも決定的瞬間を記録できる信頼の置ける相棒でした。この実績が「壊れないニコン」という神話を確固たるものにしたのです。
ニコンFが伝説となった3つの核心
- 圧倒的な堅牢性:贅沢な素材を用いたボディと、画期的なチタン幕シャッターによる、あらゆる物理的衝撃や過酷な環境に耐えうるタフネス。
- 絶対的な信頼性:戦場という極限の状況下でプロカメラマンたちに証明された、いかなる時も確実に動作するという機械としての誠実さ。
- 完成されたシステム性:あらゆる撮影シーンをカバーする50本以上の豊富な交換レンズ群や、世界初の実用的なモータードライブなど、プロの要求に応える比類なき拡張性。
こうした歴史的価値が認められ、ニコンFは日本のカメラ産業の発展を象徴する製品として、2020年に日本機械学会より「機械遺産」に認定されました。これは、ニコンFが単なる工業製品ではなく、技術史にその名を刻む文化遺産であることを公的に証明するものです。
ニコンFの当時の価格はいくらでしたか?

その性能と信頼性でプロを魅了したニコンFですが、発売当時は庶民にとってどれほどの価値を持つ製品だったのでしょうか。
1959年(昭和34年)の発売当時、標準レンズであるNikkor-S Auto 5cm F2が付属したセットの公式な定価は67,000円でした。
この金額を現代の価値観で理解するためには、当時の物価と比較するのが最も分かりやすいでしょう。当時の国家公務員の大学卒初任給が約10,200円、一般企業でも12,000円程度でした。つまり、ニコンFを手に入れるためには、若者が半年近く、一切お金を使わずに貯金しなければならないほどの金額だったのです。これは現在の貨幣価値に換算すると、100万円から150万円、あるいはそれ以上の感覚に近いかもしれません。
昭和34年頃の物価とニコンFの価値
| 品目 | 当時の価格 | ニコンF(67,000円)で買えた量 |
|---|---|---|
| 国鉄初乗り運賃 | 10円 | 6,700回乗車分 |
| コーヒー1杯 | 約50円 | 1,340杯分 |
| 映画鑑賞料 | 約150円 | 約446回鑑賞分 |
| 葉書 | 5円 | 13,400枚分 |
このように具体的な物価と比較すると、67,000円という金額がいかに大きなものであったかが鮮明に理解できます。まさに、ごく一部のプロフェッショナルや、よほどの写真愛好家、あるいは富裕層でなければ手にすることができない、真の「高嶺の花」だったのです。
ニコンFの初期型の見分け方

ニコンFは、約15年という長い期間にわたって製造されたため、時代ごとの改良やコストダウンに伴う仕様変更が随所に見られます。これらの違いを理解することが、個体を識別する上での重要な手がかりとなります。大まかには「前期型(初期型)」「中期型」「後期型(ニューF)」の3つのグループに分類でき、それぞれに分かりやすい外観上の特徴があります。
中古カメラを見分ける際に、まず注目すべき最も基本的なポイントは、①軍艦部(カメラ上部)のメーカー名刻印、②巻き上げレバー先端の仕上げ、③セルフタイマーレバー先端の仕上げの3点です。これらの組み合わせによって、その個体がおおよそどの時期に製造されたものかを判断することができます。
前期・中期・後期の主な違い 比較表
| モデル | ① 軍艦部刻印 | ② 巻き上げレバー先端 | ③ セルフタイマーレバー先端 | おおよその製造番号 |
|---|---|---|---|---|
| 前期型(初期型) | NIPPON KOGAKU(通称:富士山マーク) | 金属製(ローレット加工) | 金属製(ギザギザ加工) | 640万台 ~ 670万台前半 |
| 中期型 | Nikon | 金属製(ローレット加工) | 金属製(ギザギザ加工) | 670万台後半 ~ 730万台前半 |
| 後期型(通称:ニューF) | Nikon | 黒いプラスチック製指当て付き | 黒いプラスチック製指当て付き | 730万台後半 ~ 745万台 |
上記の通り、前期型を決定づける最大の特徴は「富士山マーク」と呼ばれる刻印の有無です。これが中期型になると、私たちに馴染み深い「Nikon」のロゴに変更されます。そして後期型は、後継機であるニコンF2のデザイン要素が取り入れられ、操作性を向上させるための黒いプラスチック製の指当てがレバー類に追加されるのが最も大きな外観上の違いです。
まずはこの3つのポイントをマスターすれば、中古カメラ店やオンラインマーケットでニコンFを見かけた際に、一目でそのモデルの年代を大まかに特定し、その個体の価値を判断する第一歩とすることができるでしょう。Fの一桁機シリーズは、まさにニコンのプロ用旗艦機として君臨しました。歴代フラッグシップ機の変遷についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ニコンFの富士山マークについて

ニコンFの前期型を他のモデルと明確に区別し、その価値を象徴する特別なディテールが、愛好家の間で「富士山マーク」や「おにぎりマーク」として親しまれている刻印です。
この刻印は、カメラの軍艦部、フィルム巻き戻しクランクの隣に配置されているメーカー名表記を指します。そこには「NIPPON KOGAKU TOKYO」という文字が刻まれ、その中央に日本光学工業の旧ロゴマークが誇らしげに配置されています。このロゴマークの形状が、日本の象徴である富士山のシルエットに見えることから、この愛称で呼ばれるようになりました。
富士山マークが持つ歴史的価値
富士山マークは、ニコンというブランドが世界市場を席巻する以前の、「日本光学工業」という一企業の矜持とアイデンティティを雄弁に物語る、歴史的な証人です。1960年代半ばから、ニコンはグローバル戦略としてブランド名を「Nikon」に統一していく方針を打ち出し、カメラ本体の刻印も順次変更されていきました。その結果、この味わい深い刻印は中期型以降のモデルからは姿を消すことになります。
そのため、富士山マークを持つ前期型のニコンFは、単なる古いモデルというだけでなく、ニコンの歴史の転換点を示す貴重な資料としての価値を持っています。このような背景から、コレクターの間では特に人気が高く、中古市場においても、状態の良い個体は中期型以降のモデルよりも高値で取引されるのが一般的です。この小さな刻印一つに、企業の歴史と時代の空気が凝縮されているのです。
希少なニコンF 640の特徴とは

ニコンFの数あるバリエーションの中でも、コレクターやマニアの間で特別な存在として扱われ、極めて希少価値が高いとされているのが、製造番号(シリアルナンバー)が「640」から始まる、通称「640モデル」です。これは前期型の中でも、1959年の発売開始から1960年初頭にかけて製造された、まさしく最初期のグループを指します。
量産体制が完全に確立される前のモデルであるため、後のモデルとは異なる細かな仕様が数多く存在し、その一つ一つがコレクターの探究心をくすぐります。
コレクターを魅了する「640モデル」の主な特徴
- シャッター幕:現存する個体は極めて稀ですが、ごく初期のロットにはチタン幕ではなく布製シャッター幕が採用されていたという記録があります。これは歴史的にも非常に重要な特徴です。
- セルフタイマーレバー:後のモデルが縦方向の直線的なギザギザ(ローレット)であるのに対し、「640モデル」の初期に見られるのは斜め方向の綾目状のギザギザです。
- 巻き上げレバーの形状:レバー先端の切り欠きが、涙のしずくのような丸みを帯びた「涙滴型」と呼ばれる形状をしています。
- 底蓋のASA感度表示板:後のモデルではモノクロの白文字表記のみになりますが、この時代はカラーフィルム用の赤文字とモノクロ用の白文字が併記されています。
- 裏蓋内部のパテント刻印:カメラ内部、裏蓋を外した本体側に、取得した特許を示す「PAT. PEND.」などの刻印が見られる個体が存在します。
- シャッタースピードダイヤルの固定ネジ:後のモデルが2本のネジで固定されているのに対し、1本のマイナスネジで固定されているのが初期型の特徴です。
これらの特徴は、ニコンFという製品が完成形に至るまでの進化の過程、いわば試行錯誤の跡とも言えるでしょう。全ての「640モデル」にこれらの特徴が網羅されているわけではなく、製造時期によって微妙な差異が存在します。もし、これらの特徴を複数併せ持つ個体に出会うことがあれば、それは博物館級の価値を持つ、非常に貴重な一台である可能性が高いと言えます。
仕様から見るニコンF前期・後期の違い

- Nikon F アイレベルとは何ですか?
- ニコンF アイ レベルの欠点は何ですか?
- ニコンFのファインダーの外し方
- ニコンFの製造番号から製造年を特定する方法
- 結論:ニコンf前期・後期の違いまとめ
Nikon F アイレベルとは何ですか?
「Nikon F アイレベル」という言葉は、特定のモデル名ではなく、ニコンFのボディに、露出計を一切内蔵していない最もシンプルで基本的なファインダーである「アイレベルファインダー」を装着した状態を指す、愛好家の間での一般的な呼称です。
このアイレベルファインダーの最大の特徴は、何と言ってもそのデザインにあります。正面から見たときに鋭利な三角形のシルエットを描くその形状は、「三角頭」や「とんがり頭」という愛称で親しまれ、ニコンFというカメラのアイデンティティを最も象徴するパーツとして広く認識されています。
この機能美あふれる洗練されたデザインは、1964年の東京オリンピックの公式ポスターを手掛けたことでも知られる、日本を代表するグラフィックデザイナー・亀倉雄策氏によるものです。伝えられるところによると、製造現場からは「先端が鋭すぎて、プレス加工時に金属が破れてしまう」と難色が示されたそうですが、亀倉氏が「このラインでなければ意味がない」と一切のデザイン変更を認めなかったことで、技術者たちの創意工夫の末にこの唯一無二のスタイリッシュなフォルムが実現したと言われています。
アイレベルファインダーが選ばれる理由(メリット)
- 究極のデザイン性:機能から導き出された、一切の無駄を削ぎ落としたシャープで美しいデザインは、時代を超えて人々を魅了します。
- 軽量・コンパクト:露出計や電池スペースなどの電子部品がないため、後述するフォトミックファインダーと比較して著しく小型で軽量です。軽快なスナップ撮影に向いています。
- 高い信頼性とメンテナンス性:構造が単純な機械部品のみで構成されているため、電子的な故障のリスクが皆無です。また、電池も不要なため、いつでもどこでも撮影が可能です。
もちろん、露出計が内蔵されていないため、撮影者は単体の露出計を使用するか、「サニー16ルール」に代表されるような経験則に基づいて露出を自ら判断する必要があります。
しかし、この一見不便とも思える一手間こそが、光を読み、カメラを完全に自分のコントロール下に置くという、フィルム写真本来の醍醐味であると感じるユーザーも少なくありません。そのため、現在の中古市場においても、ニコンFといえば、この美しいアイレベルファインダー付きのスタイルが最も人気を集めています。
ニコンF アイ レベルの欠点は何ですか?

その完成されたデザインと機械的な信頼性で多くのファンを持つNikon F アイレベルですが、60年以上前に設計されたカメラであるため、現代のカメラの利便性に慣れた視点から見ると、いくつかの「欠点」あるいは乗り越えるべき「個性」とも言える特徴が存在します。これらを事前に理解しておくことは、購入後のミスマッチを防ぎ、末永く付き合っていくために非常に重要です。
購入前に知っておきたいアイレベルモデルの3つの特徴
- 露出計が内蔵されていない
最も大きな特徴であり、最大の注意点です。前述の通り、アイレベルファインダーには露出を測定する機能が一切ありません。適正な明るさの写真を得るためには、スマートフォン用の露出計アプリや単体の露出計を別途用意する必要があります。あるいは、晴れの日の日中なら絞りをF16に設定し、シャッタースピードをフィルム感度の逆数にする(例:ISO100なら1/125秒)という「サニー16ルール」を覚えるなど、撮影者自身が光を読むスキルを身につけることが求められます。これは初心者にとっては、フィルムを無駄にしてしまうリスクを伴う高いハードルかもしれません。 - 人間工学的に配慮されていないシャッターボタン位置
ニコンFのシャッターボタンは、現代のカメラのように指が自然に届くボディ前面のグリップ部ではなく、軍艦部の上面、しかもかなり後ろ寄りに配置されています。これは母体となったレンジファインダーカメラ「ニコンSP」の設計をそのまま引き継いだためですが、グリップを深く握る現代のスタイルでは、人差し指を不自然に曲げる必要があり、特に縦位置での撮影時に手ブレを誘発しやすいと指摘されています。この点は、純正アクセサリーのソフトシャッターレリーズ(AR-1など)を装着することで、ボタンの高さがかさ上げされ、格段に押しやすくなります。 - アクセサリー拡張性が低いファインダー接眼部
前期型から中期型にかけて採用されていた長方形の接眼部(通称:四角窓)は、視度補正レンズやマグニファイヤーといったアクセサリーを直接ねじ込むためのネジが切られていません。これらのアクセサリーを使用するには、丸窓に変換する特殊なアダプターが必要となり、入手は困難です。アクセサリーを活用した撮影を考えている場合は、ネジが切られている丸窓に変更された中期以降のモデルを選ぶのが賢明です。
これらの点は、現代のオートマチックなカメラから見れば紛れもない「欠点」です。しかし、見方を変えれば、カメラの基本である「露出」を学び、機材の特性を理解し、工夫を凝らして使いこなすという、クラシックカメラならではの「対話する楽しみ」を与えてくれる魅力的な「個性」と捉えることもできるでしょう。
ニコンFのファインダーの外し方

ニコンFのシステムカメラとしての柔軟性を象徴する機能が、ユーザー自身の手で簡単にファインダーユニットを交換できることです。
標準のアイレベルファインダーから、露出計を内蔵した各種フォトミックファインダーへ交換したり、あるいはファインダー内部や接眼レンズの清掃のために取り外したりする際には、正しい手順を覚えておくことが重要です。破損を防ぐためにも、無理な力を加えないようにしましょう。
ファインダーの着脱は、以下の簡単な手順で行うことができます。
ファインダーの安全な着脱手順
- カメラを安定した場所に置き、背面を自分の方に向けます。ファインダー接眼レンズの左隣(巻き戻しクランク側)に、小さな円形の「ファインダー着脱ボタン」があるのを確認してください。
- このボタンを、爪の先や先の細いもので「カチッ」と音がするまで、あるいはそれ以上動かなくなるまでしっかりと押し込みます。このボタンがロックを解除するスイッチになります。
- ボタンを完全に押し込んだ状態を維持したまま、もう片方の手でファインダーユニット全体を掴み、ゆっくりと真上に持ち上げます。スムーズに外れるはずです。
取り扱い上の重要な注意点
ファインダー着脱ボタンの押し込みが不十分な場合、ロックが完全に解除されず、ファインダーは外れません。この状態で無理に引き抜こうとすると、ロック機構やファインダー側の爪、ボディ本体を破損する重大な故障に繋がります。 必ず、ボタンをしっかりと最後まで押し込むことを徹底してください。また、ファインダーを取り付ける際は、取り外した時と逆の手順で、ボディ上部の定位置にファインダーを置き、上から軽く押し込むだけです。「カチッ」という小気味良い音がすれば、ロックが掛かった合図です。
この簡単な着脱機構により、ニコンFは撮影目的に応じてその姿と機能を変化させることができました。上から覗き込む「ウエストレベルファインダー」や、眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい「アクションファインダー」など、様々なファインダーに交換することで、一台のカメラで多彩な撮影スタイルを追求することが可能です。
ニコンFの製造番号から製造年を特定する方法

お持ちの、あるいは購入を検討しているニコンFが、その長い歴史の中でいつ頃生まれた個体なのかを知るための最も確実な手がかりが、ボディ軍艦部に刻印された7桁の製造番号(シリアルナンバー)です。ニコンが公式に詳細なリストを公開しているわけではありませんが、長年の愛好家や研究者たちの調査により、どの番号帯がいつ頃製造されたかがある程度判明しています。
ここに掲載する対応表は、中古カメラ市場で一般的に参照されているものです。あなたのニコンFの「戸籍」を調べる際の参考にしてください。
製造番号と製造年のおおよその対応表
| 製造番号(上3桁) | おおよその製造年 | 主なモデル分類 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 640 - 641 | 1959年 - 1960年 | 前期型 | 「640」は最初期モデルとして特に希少。 |
| 642 - 649 | 1960年 - 1962年 | 細かな仕様変更が多い時期。 | |
| 650 - 659 | 1963年 - 1965年 | 安定した量産期に入る。 | |
| 660, 670 - 675 | 1965年 - 1966年 | 660番台は欠番とされる。フォトミックT対応機が登場。 | |
| 675 - 689 | 1966年 - 1968年 | 中期型 | 刻印が「Nikon」に変更される過渡期。 |
| 690 - 699 | 1968年 - 1969年 | フォトミックFTn対応のため銘板形状が変更。 | |
| 700 - 729 | 1969年 - 1971年 | 後継機F2の発売後も並行して生産。 | |
| 730 - 745 | 1972年 - 1974年 | 後期型 | 「ニューF」と呼ばれるプラスチックパーツ付きモデル。 |
この情報はあくまで目安です:繰り返しになりますが、この対応表はメーカーの公式データではなく、過去の個体調査に基づいた通説です。また、60年以上の歳月の中で、故障修理などにより異なる年代の部品が組み合わされている個体(いわゆる「ニコイチ」や「サンコイチ」と呼ばれるもの)も少なくありません。特に、ボディの製造番号とファインダーの年代が一致しないケースは頻繁に見られます。あくまで、その個体のおおよその生まれを知るための一つの参考情報として活用し、絶対的なものと考えないことが重要です。
結論:ニコンF前期・後期の違いまとめ
この記事では、カメラ史に燦然と輝く名機ニコンFについて、前期・中期・後期モデルの違いを中心に、その歴史、特徴、そして魅力の核心に迫るべく、詳細な解説をお届けしました。最後に、本記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。
この記事のポイント
- ニコンFは1959年に発売され一眼レフカメラの歴史を塗り替えた記念碑的モデルである
- 約15年間という長期にわたり生産され、その中で前期・中期・後期のバリエーションが生まれた
- 前期・中期・後期の最も分かりやすい違いは軍艦部のメーカー名刻印とレバー先端の仕上げにある
- 前期型の最大の特徴は「NIPPON KOGAKU」と記された通称「富士山マーク」である
- 中期型からはグローバルブランドである「Nikon」のロゴ刻印へと変更される
- 後期型(ニューF)は操作性向上のためレバー先端に黒いプラスチック製指当てが装着される
- 特に希少価値が高いのは製造番号が640万台から始まる「640モデル」と呼ばれる最初期型である
- 「640モデル」には布幕シャッターや斜めギザのセルフタイマーレバーなど後のモデルと異なる unique な仕様が見られる
- 「アイレベル」とは露出計のない三角形のアイレベルファインダーを装着した状態の通称を指す
- アイレベルモデルは軽量で美しいデザインが魅力だが、露出計がないため撮影者にある程度のスキルが求められる
- シャッターボタンがボディ後方にあり、現代のカメラとは異なる独特の操作感を覚える
- ファインダーは背面の着脱ボタンを押しながら真上に引き抜くことでユーザー自身が簡単に交換可能である
- 製造番号の上3桁を確認することで、その個体のおおよその製造年を推測することができる
- 発売当時の価格はレンズ付きで67,000円、これは当時の大卒初任給の約半年分に相当する非常に高価な製品だった
- 戦場でも証明された圧倒的な堅牢性と信頼性がプロカメラマンの絶大な支持を集め「伝説」となった