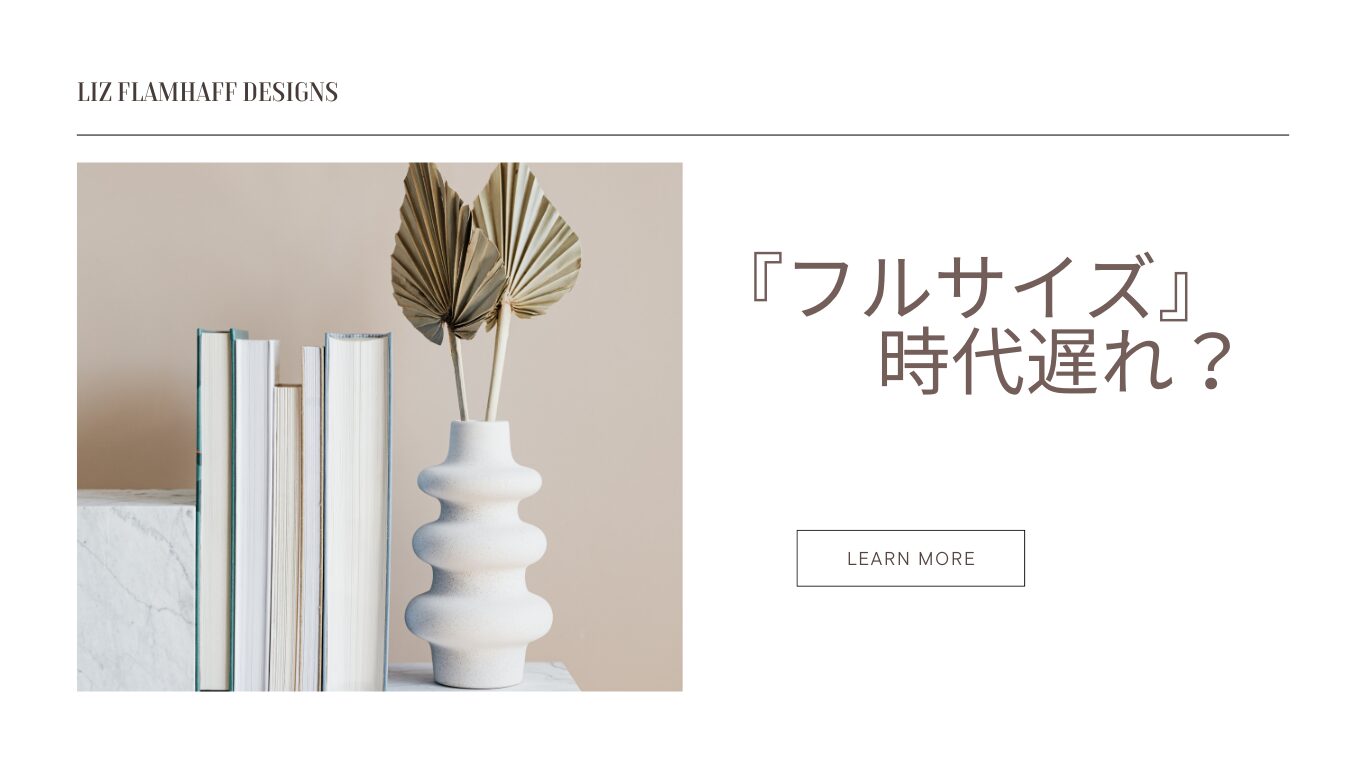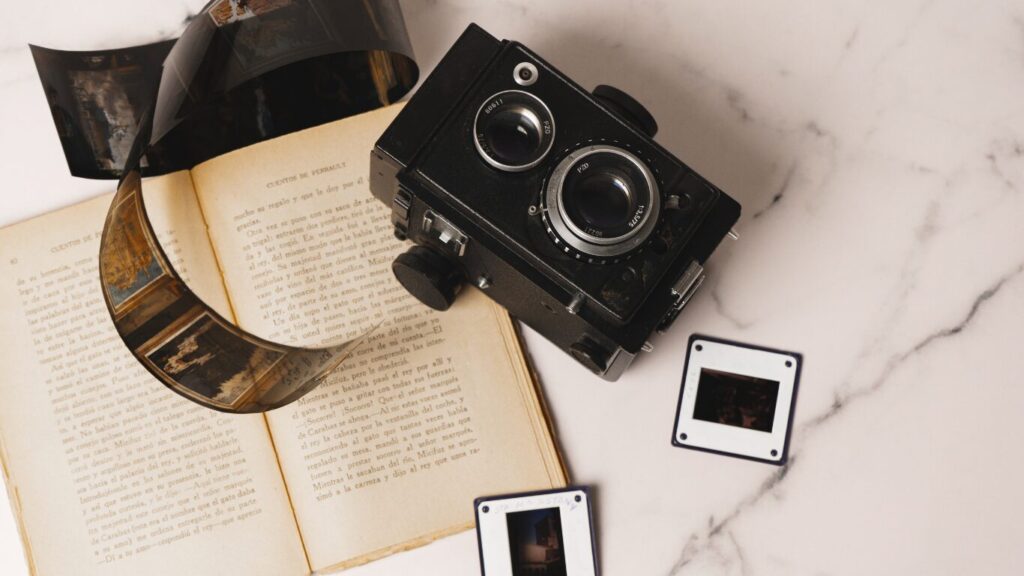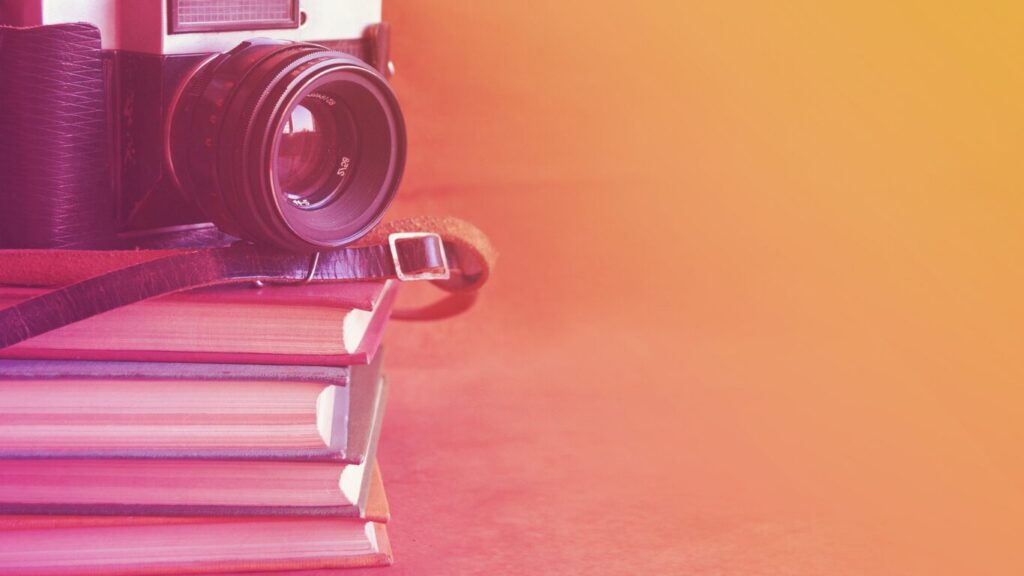カメラ選びは常に悩ましいものですが、近年「もうフルサイズはいらない」という声が増えてきています。かつてのフルサイズ至上主義から脱却し、自分に合ったカメラを選ぶ時代が来ているのです。
フルサイズを購入したものの後悔し、手放した方々の共通点は「思ったより使わなかった」というものです。一方で、富士フイルムがフルサイズ一眼を作らない理由は、APS-Cと中判での差別化戦略にあります。では、フルサイズとAPS-Cの画質比較から見ると、実際どれほどの差があるのでしょうか?ボケ表現ではフルサイズが有利ですが、最新のAPS-C機でも十分な表現が可能です。
フルサイズミラーレスの利点は高画質と豊かな表現力ですが、サイズや価格といった欠点も無視できません。また、フルサイズのレンズをAPS-Cにつけると画角が変わりますが、中心部の描写は良くなる利点もあります。初心者におすすめのフルサイズミラーレスはいくつかありますが、本当にフルサイズが必要ない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、いわゆる「フルサイズ症候群」から抜け出し、APS-Cを選ぶ理由も含めて解説します。
ポイント
- 現代のAPS-C機の画質は多くの撮影シーンでフルサイズと遜色ないレベルまで向上している
- フルサイズの重さとサイズの負担が実際の使用頻度低下につながりやすい
- フルサイズを選ぶべき具体的な撮影シーンと不要な撮影シーンの違い
- 高価なフルサイズよりもライフスタイルに合った選択をすることの重要性

大切な思い出のために・・
【タビショット】なら憧れの『カメラ』が試せる!
全ての商品保証付き。万が一の破損も0円!
もうフルサイズはいらないと言われる理由とは

- フルサイズ至上主義からの転換点
- fujifilmがフルサイズ一眼を作らない理由
- フルサイズとAPS-Cではどちらがボケやすい?
- APS-Cとフルサイズ:画質 比較から見る実力差
- APS-Cを選ぶ理由は?
- フルサイズミラーレスの利点は?
フルサイズ至上主義からの転換点
かつては「カメラ=フルサイズが最上」とされていた時代がありました。多くのユーザーがセンサーサイズの大きさこそが画質を決定づけると信じ、フルサイズ機にこだわってきたのです。しかし近年、この価値観に変化が見られるようになりました。
その背景には、APS-Cやマイクロフォーサーズといった小型センサー搭載機の進化があります。例えば、ノイズ耐性やダイナミックレンジの面でも、現代のAPS-C機は旧世代のフルサイズ機に匹敵する性能を持ち始めているのです。加えて、ボディやレンズの小型軽量化は、撮影者の負担を大きく減らします。
一方で、フルサイズ機はその大きさや価格がネックになることも少なくありません。とくに趣味で写真を楽しむ層にとっては、機材の重量やコストは導入・継続のハードルになりやすいポイントです。
このような時代背景と技術革新により、「フルサイズでなければならない」という考えから離れ、自分の用途やライフスタイルに適したセンサーサイズを選ぶ動きが加速しています。今では、「フルサイズ至上主義」は過去のものになりつつあるといえるでしょう。
fujifilmがフルサイズ一眼を作らない理由

FUJIFILM(富士フイルム)は、他社がこぞってフルサイズ市場に参入する中でも、一貫してAPS-Cおよび中判センサーの展開に注力しています。その方針には明確な戦略があります。
まず、APS-Cフォーマットにおける技術的な完成度の高さが挙げられます。富士フイルムのXシリーズでは、色再現の美しさやフィルムシミュレーション機能、レンズラインナップの充実度など、APS-Cでもプロユースに応えるクオリティを実現しています。これにより、フルサイズ機に頼らずとも十分に高画質な写真表現が可能になっています。
また、中判センサーを採用した「GFXシリーズ」によって、フルサイズよりもさらに上位の高画質を求めるユーザー層にも応えています。つまり、富士フイルムはAPS-Cと中判という2つの路線で、市場における棲み分けを実現しているのです。
もし仮にフルサイズ市場に参入した場合、競合がひしめく中で差別化が難しくなり、結果として自社の製品ポジションを不明確にしてしまう可能性があります。だからこそ富士フイルムは、あえてフルサイズを選ばないことで独自性を保ちつつ、ユーザーに最適な価値を提供し続けているのです。
フルサイズとAPS-Cではどちらがボケやすい?
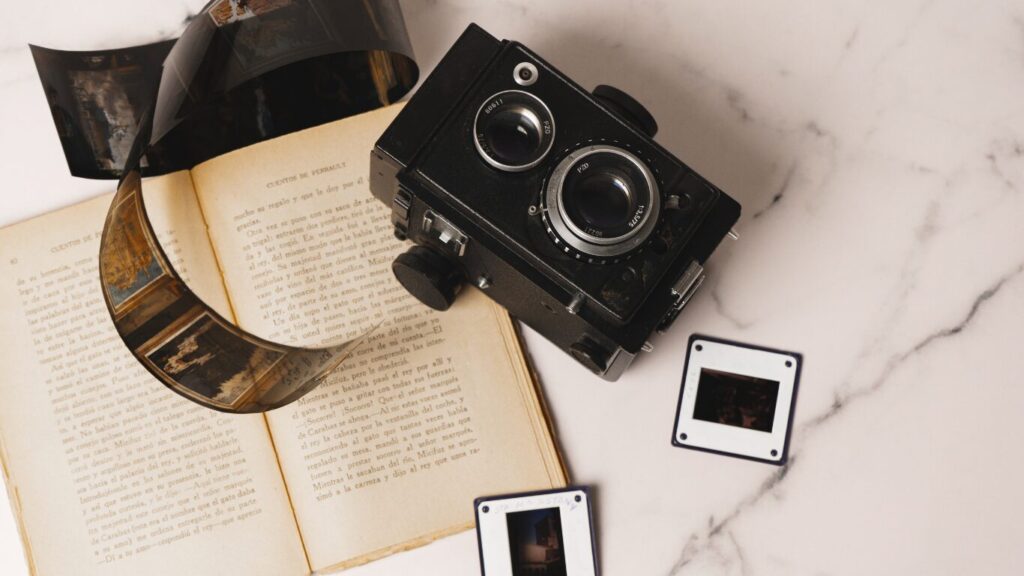
一般的に、背景を大きくぼかした写真を撮りたい場合はフルサイズの方が有利です。これは、センサーサイズが大きいことで被写界深度が浅くなりやすいためです。つまり、同じ距離・同じ絞り・同じ焦点距離で撮影した場合、フルサイズの方が背景をより滑らかにぼかせます。
一方で、APS-Cでもレンズの選び方や設定次第で十分に美しいボケ味を得ることができます。例えば、F値の小さい明るい単焦点レンズを使えば、APS-C機でも背景をしっかりとぼかす撮影は可能です。
このため、「ボケやすさ=フルサイズ一択」とは言い切れません。被写体との距離や構図、レンズの特性など、撮影条件を工夫することでAPS-Cでも十分に印象的なボケ表現ができるのです。
加えて、APS-Cの方が望遠効果が強くなるため、ポートレートや動物撮影ではフレーミングしやすく、ボケの演出に有利に働く場面もあります。
このように、ボケ味にこだわる場合はフルサイズが有利ですが、APS-Cでも撮影スキルやレンズ次第で、見劣りしない仕上がりにすることは十分に可能です。
APS-Cとフルサイズ:画質 比較から見る実力差

カメラを選ぶ際、「画質の違い」は大きな判断材料のひとつです。フルサイズはセンサーが大きいぶん、より多くの光を取り込むことができ、暗所でのノイズ耐性やダイナミックレンジで優れる傾向があります。
しかし、最近のAPS-C機の画質向上は目覚ましく、日中の撮影や適切な条件下であれば、一般的な鑑賞レベルではフルサイズとの違いを見分けにくい場面も増えてきました。SNSやWebでの使用が主であれば、APS-Cの画質で十分満足できるでしょう。
また、画質の差が出やすいのは「極端な暗所」「高ISO」「大きくトリミングする」など、特定のシチュエーションに限られます。日常的な撮影でその違いが大きな支障になることは少ないと言えます。
APS-Cには機材の軽さ、コストパフォーマンスの高さという大きなメリットもあります。こう考えると、画質だけでフルサイズを選ぶ時代は終わりつつあるのかもしれません。
つまり、「画質重視=フルサイズ」という考え方にこだわらず、自分の撮影スタイルに合ったセンサーサイズを選ぶことが、満足度の高いカメラ選びにつながります。
APS-Cを選ぶ理由は?

APS-Cを選ぶ理由は、取り回しやすさとコストパフォーマンスの良さにあります。多くのAPS-C機は、ボディやレンズがコンパクトに設計されており、日常使いや旅行に持ち出す際の負担が少ないという特長があります。
さらに、同じ性能帯のフルサイズ機に比べて価格が抑えられていることも、初心者や趣味で写真を楽しむ方にとっては大きな魅力です。撮影に必要な基本機能をしっかり備えていながら、予算内に収めやすい点は無視できません。
また、APS-Cのセンサーサイズは望遠撮影にも有利に働きます。焦点距離が1.5倍程度に換算されるため、例えば200mmのレンズを使えば実質300mm相当の画角となり、動物やスポーツなど遠くの被写体をしっかりと捉えることができます。
そしてもう一つは、カメラバッグの中が軽くなること。ボディとレンズの両方が軽量なAPS-C機材は、長時間の撮影や街歩きでの疲労を減らしてくれます。
このように考えると、APS-Cは「カメラを日常的に持ち歩きたい人」「コストを抑えつつも高画質を求める人」にとって、非常にバランスの良い選択肢と言えるでしょう。
フルサイズミラーレスの利点は?

フルサイズミラーレスの最大の利点は、表現力の幅が広いことにあります。大きなセンサーは光を豊かに取り込めるため、暗所でのノイズが少なく、細部までくっきりと描写できるのが特長です。
さらに、浅い被写界深度を活かした印象的なボケ表現がしやすく、ポートレートや商品撮影などでプロらしい仕上がりが求められる場面において強みを発揮します。背景と被写体の分離感も得やすく、立体感のある写真が撮れる点も魅力です。
また、最新のフルサイズミラーレスには、高速AFや高解像度センサー、優れた動画性能など、ハイエンドな機能が多数搭載されています。これにより、静止画も動画も一台でこなせる「オールラウンドな性能」を求める方にとっては理想的な選択肢となります。
一方で、機材が大きく重くなりがちな点や価格が高い点には注意が必要です。特に、レンズのサイズや重量がかさむことは持ち運びやすさに影響します。
このような利点と注意点を把握したうえで、「表現の質にこだわりたい」「将来的に本格的な撮影を考えている」方にとっては、フルサイズミラーレスは非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
もうフルサイズはいらない時代のカメラ選び
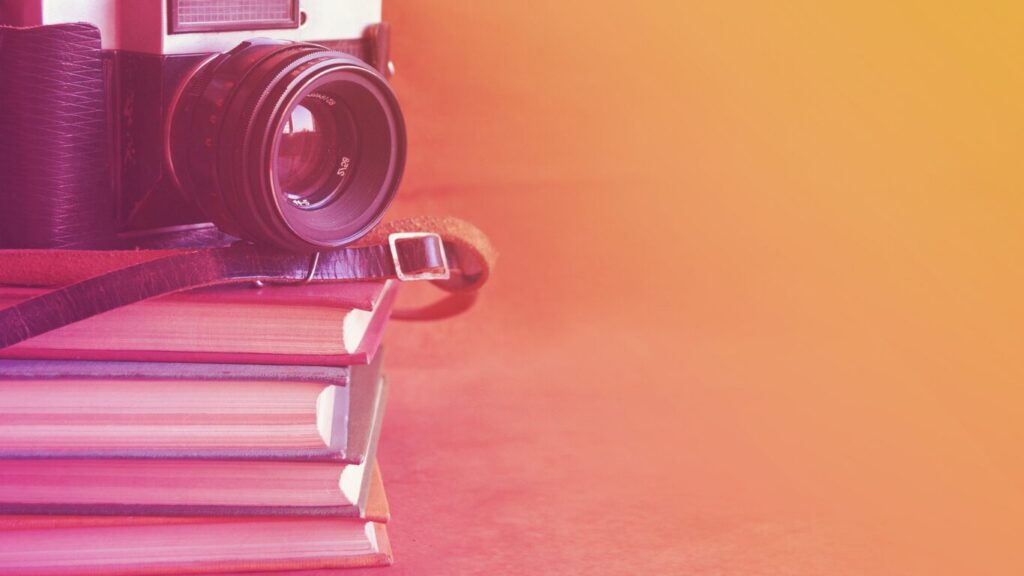
- フルサイズミラーレスに後悔する理由とは
- フルサイズを手放した人の共通点
- フルサイズの欠点は?
- フルサイズは何が良い?本当に必要?
- フルサイズのレンズをAPS-Cにつけるとどうなる?
- フルサイズで初心者におすすめのミラーレスは?
- もうフルサイズはいらない時代のカメラ選びポイント
フルサイズミラーレスに後悔する理由とは
フルサイズミラーレスに魅力を感じて購入したものの、後悔するケースも少なくありません。その理由の多くは、機材の大きさと重さ、そしてコストに関係しています。
まず、フルサイズ機は性能を重視して作られているため、ボディ自体がしっかりしており、レンズも大きくなりがちです。そのため、いざ外に持ち出そうと思ったときに、重くて億劫になってしまうという声が多く聞かれます。結果として、「高性能でも使う頻度が減ってしまった」と感じる人が後を絶ちません。
さらに、周辺機材のコストも見過ごせません。フルサイズに対応するレンズは高価なものが多く、複数のレンズを揃えようとすると、思った以上に出費がかさんでしまうこともあります。これが想定外だったと感じる人は少なくないようです。
また、初心者にとっては設定や機能が複雑すぎることも後悔につながる一因です。スペックに惹かれて購入したものの、操作に慣れるまで時間がかかり、うまく使いこなせなかったというケースもあります。
こうした理由から、「良いカメラを買ったのに楽しめない」という状況に陥ることがあり、結果としてフルサイズミラーレスを後悔する人もいるのです。
フルサイズを手放した人の共通点

フルサイズを手放した人に共通しているのは、「自分の撮影スタイルに合っていなかった」という気付きです。性能が高いことは確かですが、それが必ずしも使いやすさや満足度に直結するとは限りません。
例えば、日常のスナップや旅行での撮影がメインの人にとっては、フルサイズの重量とサイズがネックになりがちです。持ち歩くたびに負担を感じ、結局スマートフォンで済ませてしまうことも少なくありません。このようなストレスを感じる中で、「もっと軽くて扱いやすいカメラでよかった」と思うようになったという声もよく聞かれます。
また、撮影頻度が高くない場合には、フルサイズの機能を持て余してしまうこともあります。せっかく高価なカメラを買ったのに、ほとんど使わなかったという経験から、思い切って手放す選択をする人もいます。
加えて、写真の使用目的がSNSやブログ中心である場合、高解像度や細かな階調表現がそこまで求められないこともあります。APS-Cやマイクロフォーサーズの画質でも十分と感じる人にとっては、フルサイズは過剰なスペックとなってしまうのです。
このように、「自分にとって必要な性能は何か」を見極めた結果、フルサイズを手放すという判断に至った人が多く見受けられます。
フルサイズの欠点は?
フルサイズカメラには多くの利点がありますが、すべてのユーザーにとって最適とは限りません。実際には、いくつかの明確な欠点も存在しています。
まず第一に、サイズと重量が挙げられます。フルサイズセンサーに対応するボディとレンズは、どうしても大きく重くなりがちです。旅行や日常の撮影においては、この点が大きな負担となり、撮影自体を敬遠してしまう人も少なくありません。
次に、価格の問題があります。フルサイズ機は高性能である反面、ボディだけでなく、対応するレンズやアクセサリーも高価です。写真を趣味として始めたばかりの人にとっては、初期投資が大きなハードルになることがあるでしょう。
さらに、ファイルサイズの大きさも注意すべき点です。高画素のフルサイズ機では、1枚の写真データが大きく、パソコンへの保存や編集に時間とストレージ容量が必要になります。処理速度の遅いパソコンを使っている場合、作業効率が著しく低下する可能性もあります。
そしてもう一つ、フルサイズの性能を十分に引き出すためには、一定の撮影スキルが必要です。オート設定でも撮影は可能ですが、その本領を発揮するにはマニュアル操作や露出の知識が求められます。初心者にとっては、操作が複雑に感じられることもあるでしょう。
これらの要素を踏まえると、単に「高性能だから」という理由だけでフルサイズを選ぶと、後悔する可能性もあるのです。
フルサイズは何が良い?本当に必要?

フルサイズカメラの魅力は、一言で言えば「高画質と表現力の豊かさ」にあります。被写体の細部までクリアに描写できる点は、多くのフォトグラファーから高く評価されています。
特にボケの表現においては、フルサイズならではの美しい背景のぼかしが得られます。ポートレート撮影では、主役を際立たせ、印象的な一枚に仕上げやすいのが特徴です。また、暗所での撮影にも強く、ノイズを抑えたまま撮影できる点も利点の一つです。
ただし、こうした利点を活かすには、撮影するシーンや目的が明確である必要があります。例えば、作品づくりや商業撮影、プリント前提の写真などでは、フルサイズの性能が非常に効果を発揮します。一方で、SNSへの投稿や日常記録が主な用途であれば、APS-Cや他のセンサーサイズでも十分に対応可能です。
つまり、「本当に必要かどうか」は、その人の撮影スタイルや目的次第と言えます。使いこなせば非常に強力なツールになりますが、すべての人にとって最適な選択ではないことも忘れてはいけません。選ぶ際には、ライフスタイルとのバランスも考慮するとよいでしょう。
フルサイズのレンズをAPS-Cにつけるとどうなる?
フルサイズ対応のレンズをAPS-Cセンサー搭載のカメラに装着することは可能です。しかし、この組み合わせにはいくつかの注意点があります。
まず大きな変化として「画角が変わる」点が挙げられます。APS-Cセンサーはフルサイズよりも小さいため、同じレンズでも写る範囲が狭くなります。一般的に、焦点距離が約1.5倍に換算されるため、例えば50mmのレンズは75mm相当の望遠寄りの画角になります。これにより、広角レンズを使っても思ったほど広く写らないと感じることがあります。
また、レンズ本来の描写力が十分に活かせない場面もあります。フルサイズレンズは大きなイメージサークルを持っているため、APS-Cでは中央部分しか使用されません。そのため、周辺の描写の甘さや光量落ちといった欠点が見えにくくなる一方で、レンズの性能をフルに体感することは難しくなります。
逆に言えば、中心部の解像度が高くなることもあり、シャープな写りを期待できるというメリットもあります。ただし、その分レンズのサイズや重さはAPS-C専用レンズより大きくなるため、携帯性やバランスの面で不便を感じることもあるでしょう。
このように、装着自体は問題ありませんが、得られる画角や使い勝手は変化します。撮影目的やスタイルに合わせて判断することが重要です。
フルサイズで初心者におすすめのミラーレスは?

初心者向けにフルサイズミラーレスを選ぶ際は、「操作のわかりやすさ」「価格の手頃さ」「機能のバランス」の3点が重要になります。これらを踏まえると、いくつかのモデルが候補に挙げられます。
例えば、Canonの「EOS」は比較的軽量かつ直感的な操作が可能で、初心者でも扱いやすい機種です。AF性能も高く、人物撮影や動体撮影にも強いため、幅広いシーンに対応できます。
また、Sonyの「α7C II」はコンパクトなボディにフルサイズセンサーを搭載しており、持ち運びやすさを重視したい方に向いています。バリアングルモニターや高性能な手ブレ補正も搭載しており、動画にも挑戦したい人にも適しています。
Nikonの「Z5」も人気のエントリーモデルで、比較的価格が抑えられている点が魅力です。シンプルなメニュー構成と堅牢なボディ設計で、初心者が安心して長く使える設計になっています。
ただし、フルサイズは本体だけでなくレンズやアクセサリーも高価になりがちです。最初のうちは、キットレンズ付きのモデルから始めて、徐々にレンズを揃えていく方法も検討すると良いでしょう。
このように、初心者でも扱いやすいモデルは増えてきていますが、自分の撮影スタイルや予算に合った1台を選ぶことが、長く写真を楽しむための第一歩となります。
もうフルサイズはいらない時代のカメラ選びポイント
この記事のポイント
- フルサイズ至上主義の考え方は技術革新により過去のものになりつつある
- 現代のAPS-C機は旧世代のフルサイズ機に匹敵する性能を持ち始めている
- APS-Cはボディやレンズの小型軽量化により撮影者の負担を大幅に軽減する
- フルサイズ機は大きさや価格が導入・継続のハードルになりやすい
- 富士フイルムはAPS-Cと中判という2つの路線で市場の棲み分けを実現している
- フルサイズは背景ボケ表現が豊かだが、APS-Cも明るいレンズで十分な表現が可能
- APS-Cは望遠効果が強くなるため、ポートレートや動物撮影で有利な場面もある
- 日中や適切な条件下ではAPS-Cとフルサイズとの画質差を見分けにくい状況が増加
- SNSやWeb用途であればAPS-Cの画質で十分満足できる水準に達している
- フルサイズを手放す人は「自分の撮影スタイルに合わなかった」という共通点がある
- フルサイズの重さに負担を感じ、結局使用頻度が下がる事例が多い
- フルサイズ対応レンズはコストが高く、複数揃えると想定外の出費がかさむ
- 高解像度フルサイズはファイルサイズが大きく、保存・編集に負担がかかる
- 初心者にとってはフルサイズ機の複雑な設定や機能が使いこなしにくい場合がある
- 自分の撮影目的やライフスタイルに合ったセンサーサイズを選ぶことが重要である
関連記事